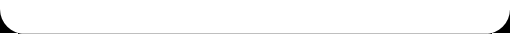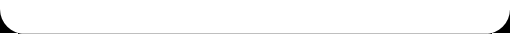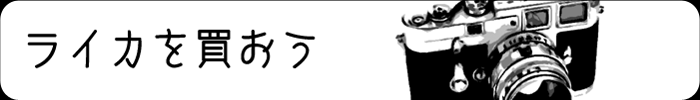レンズを付ける
 とりあえずレンズを付けてみる。沈胴レンズは必ず引き出した状態にすること。そうしないとレンズ後端がボディー内部を傷つけるおそれがある。
とりあえずレンズを付けてみる。沈胴レンズは必ず引き出した状態にすること。そうしないとレンズ後端がボディー内部を傷つけるおそれがある。
無限遠でロックできるものはロックした状態のままでよい。
どこかの本には最短撮影距離までレンズを繰り出した状態の方が良い、としてあるものもある。おそらく、無限遠より最短撮影距離の方が距離計コロの最初のヘコミが少なくなるためなのだろうが、そんなことで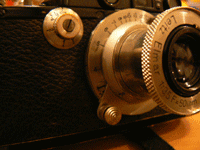 距離計が狂うことなどないので関係ないだろう。
距離計が狂うことなどないので関係ないだろう。
注意するレンズとしては、Mマントのレンズであるがダブルヘリコイドを持つデュアルレンジ・ズミクロンで、これは最短撮影距離のまま装着すると距離計コロがヘリコイドの段差に落ち込み、結構ショックを与えることになる。
レンズを時計回りにボディーにねじ込む。スクリューマウントは定位置がアバウトなのであまり気にしない。エルマーだったら写真のように無限ロックの位置がこのくらいに止まれば良いだろう。これより大きくずれるようならチョットおかしいレンズか、ボディーなのかもしれない。
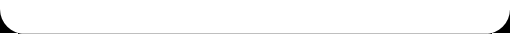
シャッターを切る
 レンズを付けて、フィルムを入れて、今度はシャッターを切ってみる。
レンズを付けて、フィルムを入れて、今度はシャッターを切ってみる。
左写真のノブを矢印方向に止まるまで回し回し、隣にあるシャッターボタンを押せばシャッターが切れる。フィルムを入れたら、最初に必ず2回ほどシャッターを切る。フィルム装着の際に露光してしまったフィルムを巻き上げるためだ。
 2回シャッターを切ったら、巻き上げノブ下のフィルムカウンターを手動で0に合わせる。
2回シャッターを切ったら、巻き上げノブ下のフィルムカウンターを手動で0に合わせる。
 ここでライカのお作法。シャッター速度設定ダイヤル(左写真)は、必ず巻き上げてから設定を行う。このダイヤルはシャッターを切ったと共に回転する。巻き上げた状態でないとダイヤルは明後日方を向いているので、どの速度に設定しているのか分からない。
ここでライカのお作法。シャッター速度設定ダイヤル(左写真)は、必ず巻き上げてから設定を行う。このダイヤルはシャッターを切ったと共に回転する。巻き上げた状態でないとダイヤルは明後日方を向いているので、どの速度に設定しているのか分からない。
シャッターダイヤルは上に持ち上げて、写真ではわかりにくいがアクセサリシュー横の-に設定したい数字を合わせる。ちなみに1/1000は少し浮いたような状態になるが、故障ではない。
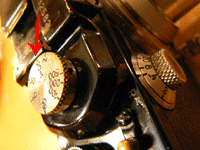 スロー速度(1/20、1/30以下)のある機種は上部ダイヤルの速度を1/20-1(あるいは1/30-1)に合わせると、ボディー全面のダイヤルが優先になる。写真では1/4秒に合わせてある。
スロー速度(1/20、1/30以下)のある機種は上部ダイヤルの速度を1/20-1(あるいは1/30-1)に合わせると、ボディー全面のダイヤルが優先になる。写真では1/4秒に合わせてある。
こうして速度設定してシャッターを切る。はっきり言うと、バルナック型ライカはシャッター速度優先で絞りをちょこまか動かす撮影方法になる。
注意点としては、シャッターボタンをゆっくり切ったときと早く押し込んだときでは微妙にシャッター速度が違ってくるし、シャッター幕と同じに動く上部のシャッターダイヤルは撮影の際に触れると、これまた速度が変わってしまう。
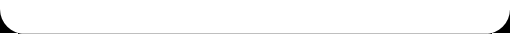
距離を合わせ、フレーミング
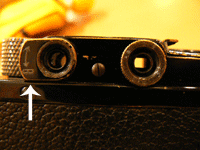 シャッターボタンを押す前に、距離を合わせフレーミングしなければならない。
シャッターボタンを押す前に、距離を合わせフレーミングしなければならない。
バルナック型ライカはM型ライカのように一眼式二重像ではないので、写真のようにピント合わせとフレーミングのファインダーは別々である。左側が二重像のピント用で、右がフレーミングファインダーである。ちなみに矢印は視度補正である。この機種はDⅢであるから、この位置に装備されているがⅢbからは巻き戻しノブの下に付くようになった。
二重像はM型のようにはっきりしたものでなく境目の分からないものである。輪郭の分かりやすいものを見つけて合わせるのがよい。
二重像を合致させたら、目を右にずらし構図を決める。Ⅲaまではこの写真のように2つの窓が離れているが、それ以降の機種は2mmに接近した。
 ファインダーは50㎜レンズに合わせてあり、結構アバウトなもので、M型ライカのようにフレーム枠などない(Ⅲgは別だが)。撮影範囲が小さく見えるだけだ。この点ほとんど1眼レフのファインダーである。
ファインダーは50㎜レンズに合わせてあり、結構アバウトなもので、M型ライカのようにフレーム枠などない(Ⅲgは別だが)。撮影範囲が小さく見えるだけだ。この点ほとんど1眼レフのファインダーである。
50㎜レンズ以外(Ⅲgは90㎜フレームもある)は外付けのファインダーに頼らなければならない。いっそのこと50㎜もファインダーを付けて見ることをお勧めする。
ライカ純正のファインダーの中では最も廉価で、しかも状態も良いものが多い。しかし、その見え具合はライカファインダーの中でトップクラスだ。
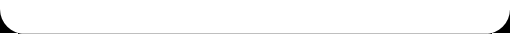
フィルムを巻き戻す
 これ以上、フィルムが巻きあがらなくなったら撮影終了である。フィルムを巻き戻す。通常、撮影中は写真の丸印内のレバーがAの位置にある。
これ以上、フィルムが巻きあがらなくなったら撮影終了である。フィルムを巻き戻す。通常、撮影中は写真の丸印内のレバーがAの位置にある。
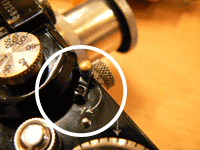 これのレバーを左の写真のようにRの位置にする。これで巻き戻しが出来るようになる。
これのレバーを左の写真のようにRの位置にする。これで巻き戻しが出来るようになる。
 巻き戻しノブを上に引き出し、矢印方向に回転させ巻き戻す。スプールにフィルムを差し込んであるので、巻き戻しの最後は堅くとも強引に巻き戻すとスプールからフィルムが抜ける。
巻き戻しノブを上に引き出し、矢印方向に回転させ巻き戻す。スプールにフィルムを差し込んであるので、巻き戻しの最後は堅くとも強引に巻き戻すとスプールからフィルムが抜ける。
フィルムベロを残したいときはスプールからフィルムがはずれたら、後は加減して巻き戻すだけ。
底蓋をあけフィルムを取り出せばお終い。